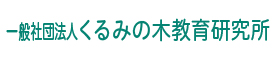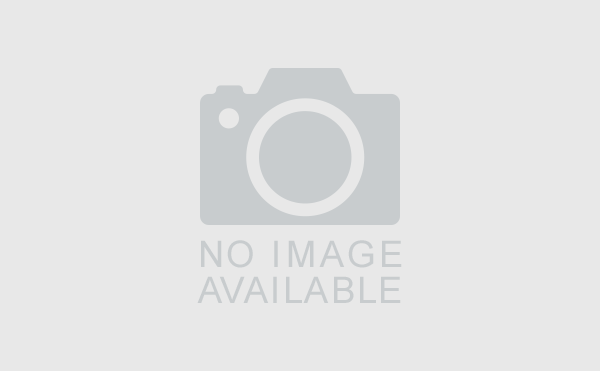お便り秋号♪
おたより、お手元に届き始めていると思います。
今回のテーマは「私達だからできる 気になる子ども達への配慮・関わり」
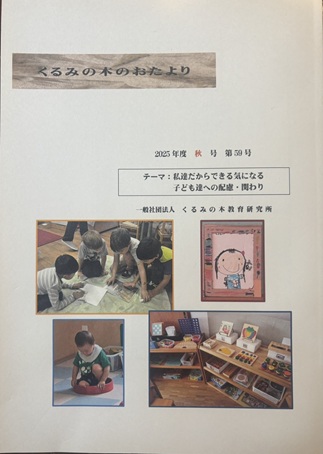
気になるなーと思う子どもたち、増えていますよね。
それを理由に「だからクラスが落ち着かない」「だから、保育が上手くいかない」という話を聞かされることも多いですが…
うーん(^^;
新学期ははるか昔で、今は10月。
確かに、大変かもしれないけれど、もし、ここまでの間にできることを頑張り続けていたら、落ち着かなかった子ども達も落ち着き始め、クラスに馴染み始め、クラス全体も落ち着き始めている(落ち着き始める気配が見えてきている)時期です。
もしくは、3歳ぐらいまでは本当に大変だったけど、年中の半ば、年長の半ばに入って急に落ち着き始めました…という子ども達、クラスも出てきている時期です。
いや、うちにいる子どもはスペシャルなんです!という場合も、それが本当にそうなのかどうかという問題もあるし(「大変!」と言い続けてきただけで、その子達に必要な具体的なことを実はしてこなかったクラスも相当数ありそうです)、それに対して園としてどう対応しているのか‥‥というと、できることはまだまだあるなーというのが実感です。
私達保育士は、脳神経の専門家でもないし、心理士でもないし、運動療法士でもないし・・・・つまり、各分野に関するプロフェッショナルな専門知識を持っているわけではありません(それは自覚した方がいいし、だからこそ、勉強もしないといけないですね)。
でも、子ども全体を一日を通して見て関わる立場にいます。
そんな私達だからこそできること、しなければいけないことをまとめてみました。
気になるなーという子ども達も、明らかに課題がある子ども達も、いずれは大人になり社会生活を送るようになる・・・子ども達の将来に対して責任を持ちながら保育を考えたいですね!
(…だから、ご飯の順番がどうのこうのというようなレベル、そこだけをピックアップして担当制やくるみですすめている保育を批判されると、なんだかなーと思ってしまうのですね^^;)