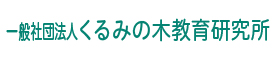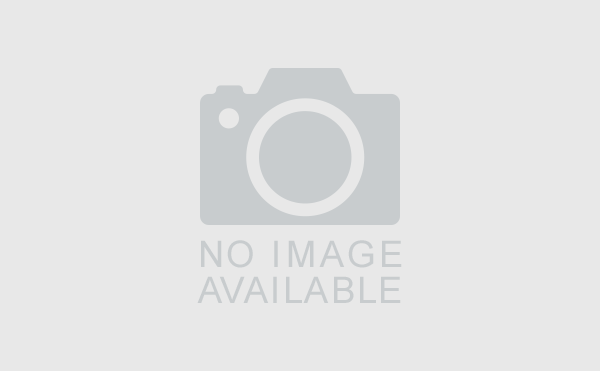大人の役割 その①
いったいどういう反動で、こんなにも「子どもの自由」がどこまででも適応されるようになってしまったんでしょうね?
(…どういう反動かは想像はつきますが、それにしても…です)
子どもはもちろん自由に、伸び伸びと育つ必要があるけれども、でも、社会で生きていく以上、様々なことも学ばなければなりません。
そして、それを教えていくのが大人。
特に、保育関係者は、それを専門とした人達。
子どもの成長、発達にとって大切なことは、子どもの発達に合わせて大人が決め、子どもに合わせて伝えていきます。
例えば、果物を食べる順番。(過去に一度書いていますが、やっぱり気になる)
一部の地域ではかなり主流になっているようで、一歳が最初からバナナを食べているのを見るたびに「そりゃあお腹いっぱいになっちゃうねー」と思うのです。
いつ食べるかは子どもが決めたらいい…それを大人が決める必要はないという主張らしいですが、でも、果物はデザートです(^^;
デザートには口の中をさっぱりさせたり、食後の楽しみの意味もありますよね。
それに、糖分を先に食べると血糖値をあげてしまう…は大人の世界では常識だし、ということは、そういう食習慣はつけない方がいいということになります。
つまり、最初に甘いものから食べる習慣はつけない方がいい。
もう一つ、大人の世界で、レストランでデザートから食べることはありません。(料理に果物が入っているのは別)
お茶碗の持ち方、スプーンの持ち方、食べる姿勢…を教えるのと同じく、こういった食事の順番(海外なら、スープ、メインディッシュ、デザートとコーヒー)も、保育園で教えたいことです。
子どもは、保育園で教えてもらっていることは、そのまま社会でも通用すること、と思っているはず。
ご飯、お味噌汁、おかずをどういう順番で食べるかは子ども達が食べたらいいけれど、でも、おかずしか目に入らずに、ご飯が後回しになってしまう子どもには「ご飯も食べようね」って言いますよね?
子どもによっては、気になった物しか目に入らないことがあるので「こっちにお魚もあるよ、美味しいよ」「お味噌汁、サツマイモが入っているよ」と言ったり、視野を広げる声かけも大切です。
「嫌い」と思っている食材が調理法で美味しいこともあるし、食べてみたら美味しかった!ということもあるので、食べれる量に減らしていいよ、ではなく「美味しいよ!」って出すことも必要です。
一方で、食べる順番を大人都合で決めているところもありますね。
お汁から食べてしまう子がいるからとお汁を後から出したり。
それならお茶かお水を用意してあげれば、水分補給の代わりにお味噌汁を飲み干してしまうこともないかもしれません。
こぼしてしまう子がいるなら、お椀の扱い方を教える。
子どもが自由に選んだり、主体的に判断できるようになるのは、たくさんの基本を教えてもらった時です。
そうしたら、今日はお腹が空いていないからお汁とデザートだけにしようかな、と決められるようになりますね。
・・・でも、きっとそれは許されないんだろうな(^^;