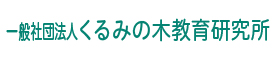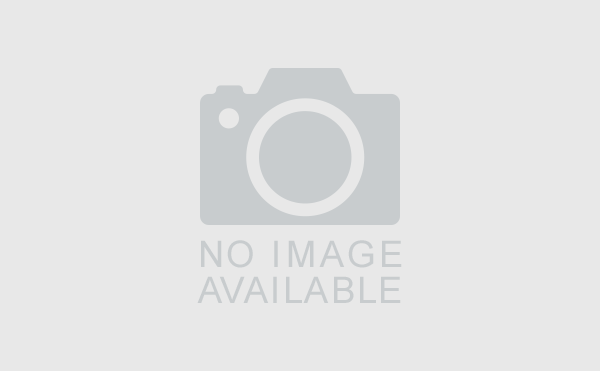たくさんの積み重ね
新学期が始まって2ヶ月経ちますね~
クラスの様子はいかがですか?
落ち着き始めました…というところもあれば、まだまだ大変です(涙)という園も多いと思います。
でも、まだまだ大変なのには理由があるはず、焦らずに、一つずつ解決していきましょうね♪
クラスが落ち着き始めるまでの日々は大変です。
子ども達は保育園にくること自体が理解できない。
最初から、お母さんと離れることにショックを受ける子ども達もいて、それはそうですよねー。
生まれてから、お母さんが全部教えてくれて、自分の命を支えてくれていたのだから。
そんな人が突然いなくなったら、それはそれは恐ろしいと思います。
最初は楽しく来ていても「え、これが毎日続くの?!!」と気が付いた辺りから悲しくなり始める子もいます。
大人と子どもの関係ができていないので、言葉を受け入れてもらえない(大人の言葉が通じない、大人の方もどう伝えたら伝わるのかが分からない)。
それでも、一緒に生活していくためにはたくさんのことを子どもたちに伝えていく必要があります。
どこに何があるのか。
どこで何をするのか。
いつ、どんな流れで行うのか。
おむつ交換はだいたいいつ頃行うのか。
ご飯も、いつごろ、どこで、誰と食べるのか。
こういうことを毎日毎日伝えていくうちに、子ども達は保育園での生活を理解し、見通しが持てるようになり、自分を見てくれる大人との信頼関係もできて安心して過ごせるようになっていきます。
ここで大切なのは、出発点は子どもであること。
生活の流れもあそびの環境も、クラスの子ども一人ひとりに合ったものにしなければ意味がないので、新学期は、それはそれは試行錯誤しながらの日々です。
育児担当制をしている園の先生たちは、一生でこんなに頭を使うことはなかったですというぐらい、頭を使いながら、悩みながら保育をしていると思います。
18人の1歳児クラスが5月の終わりに落ち着いている時・・・これはもう、先生たちが子どもたち一人ひとりのことを考え、クラスの大人が協働しながら、園もサポートしながら保育を積み重ねてきた努力の結果としか言いようがありません。
大人が自分たちの都合で子ども達を動かしているから子ども達が従順に言うことを聞くのでは絶対に!!ありません。
大人が、子どもたち一人ひとりの生活全体の日課を考え、それをクラス全体の日課として組み立て、そして、それを元に大人の動きを考える。それができていなければ、5月の終わりにクラスは落ち着きません。
「日課」を大人が子ども達を動かすためのものだと勝手な解釈をして批判をする方たちがいますが、そもそもの理解が間違っていますね(^^;
ちなみに、日課でもデイリーでも何でもいいのですが、くるみの木では育児担当制を考えたハンガリーで使っているnapirendの直訳語の日課という言葉を使っています。
napirendという単語は、ハンガリーでは「決まった生活の流れ」という意味で、ごく普通に使われます。
だから、保育園用語でも何でもなく、保護者や近所の人に「子ども達の日課が…」と言っても、ごく普通に伝わります。
生活の流れって大切ですよ。
私たちは家でも、生活の流れを作ります。
一人で生活していても、家族と一緒でも、生活の流れはあるはずです。
何時ごろに起きて、何時ごろにご飯を食べて、何時ごろにお風呂に入って…それは、子どもが好きなようにするのではなくて、だいたいの時間が決まっているはずです。
ましてや、保育園のように大勢の子ども達が一緒に生活する場では、大きな生活の流れを作ってあげなければ、一人ひとりに丁寧に、その子に合わせて対応することは不可能です。
1歳児が4人クラス、5人クラスの園なんてほぼないはずで(だとしても、今の課題のある子達の多い中ではかなり難しいはず)、12人、18人クラスがほとんどですよね?
もう一つ、担当制を「小さなグループでの活動」と解釈している場合、それ自体が間違っています。
本来の育児担当制をしている先生達がこの「小さなグループ」と聞いても、「?」となると思います。
育児担当制では、育児の場面は担当の大人が適切な人数で関わりますが、小さなグループで活動することはありません。
適切な人数:
オムツ交換 0歳、1歳クラスでは1対1、2歳児クラスでは2対1。
食事 子どもの自立度に合わせて0歳クラスは1対1→2対1、1歳児クラスは1対1→4対1、2歳児クラスは多くの園では4対1→6対1
どのタイミングで人数を増やしていくかも、子どもの発達や自立度を見ながら考えます。
批判する方たちは、本当にきちんと育児担当制をしている園の、日々の保育を朝から夕方まで、年度の初めから終わりまで、0歳から5歳まですべて見て、それでも、子ども達が育っていない、自立できていなくて、就学にもふさわしくなく、社会性も育っていないし、知的にも運動発達も問題がある子がいっぱいいる‥‥と判断した時に批判したらいいともいます。
でも、実際にちゃんと担当制をして0歳から5歳までの保育を積み重ねている園では、その真逆のはずです。
大人達が0歳から子ども個々の課題も把握しながら関わっているので、課題のある子ども達の育ちも普通の園と比べるとかなり違うはずです。
育児担当制をしている先生たちは本当に本当に細かいことまで考えながら、保育を積み重ねています。
限られた大人の数の中で、子どもたち皆が安全に遊べるよう、発達の援助もして・・・と、クラス全体に目を配りながら本当に良く動きます(育児担当制園の保育士さんたちに万歩計をつけたら、そうではない園とかなりの差が出ると思います^^;)。
子ども達が安心して過ごしているのが一番大切。
育児担当制が理解できない方は理解できなくても良いので、たくさんの頑張っている先生たちのためにも、安易に批判しないでほしいなーと思うのでした。